突然ですが、僕は、しゃべるのが得意なほうではなかったりしてます、
結構話をしていると、相手をピリッとさせてしまったり、そういった失敗がよくあります。
そんな話し方についてについて改善できる方法はないかなと思って、出会った今回の勉強の本はこちら、

「話し方で損する人得する人 五百田達成著 ディスカヴァー・トゥエンティワン出版」
はい、どこかで聞いたテレビ番組みたいな題名の名前だなーと思いながら本をとりましたが、
本を開いてからすぐ導入のページで、この本を買った時のセリフという題材で、損をするセリフとして「この本、買ってよ!」という少々反感を買うセリフを最初に出して、次に得をするセリフとして「この本を手にとってくださり、ありがとうございます」を出す、そういった損するセリフと得するセリフの実例が1ページ目から始まって、
その文章を切り口に人から「損な印象」と「得な印象」を得られる「話し方」の違いから人生が変わるといった導入から始まり、
著者の五百田達成さんもしゃべるのが不得意であった昔から、編集者、広告プランナー、作家、心理カウンセラーとコミュニケーションのプロになっていったという経験に基づいた自己紹介があることから、この本の著者の説得力の裏付けにもなり、そののちに本編に入ります。
本編は
1・家族・友人編
日常生活でもめたりしにくくしたり信頼されるフレーズをメインに解説した章。
例えば損する方は「相手の話をきっかけに自分の話を始める」といった内容で、会話の実例で相手の会話を途切れさせる損な人になります。
逆に得をする人は、「相手が話し始めたら「聞き役」に徹する」といった内容で、「聞く姿勢」を持つことで頭一つ好印象に抜け出ることができると言ってます。
2・飲み会・デート編
誘われやすい話し方の解説や、意中の相手に好印象に思われる話し方を書いた章。
例えば損する方は「自分のことをひた隠しにする」人で、色々話題を振ってものらりくらりとかわされてしまうと、相手を信頼してないように映ってしまうようです。
逆に得をする人は、「適度に自分の話をする」人で、もし自己開示が不得意な人は、「共通点の話題」もしくは「第3者の話」から入って相手に自分のことを知ってもらうことで得な話に持っていきやすくなるそうです。
3・職場・ビジネス編
職場での評価アップや、信頼度アップでできる人に見えるようになる章。
例えば損する方は「問題点ばかり指摘する」例えば上司に見せに行ってダメ出しだらけだとやる気がなくなる、そんな経験が僕もあったり、僕自身も上司に難しい理由を挙げてよくもめごとになります。
逆に得をする人は、「いいところを指摘する」という内容で、例えばまず「いいね」や「ありがとう」といった内容から入ることでポジティブに上げていき、問題点を指摘するにしても、「ここをこうしたらいい」といったいい方に持っていくようにすることで、ネガティブな言い方は減っていきます。
4・ちょっとした言い換えで「得するフレーズ」厳選15
厳選したよくある言い方15選の一言をそれぞれ損な言い方を得な言い方に直した章。
ここでは「逆に」→「それで言うと」といったように短文で15種類のよくあるフレーズが描かれてます
この4つのセクションに分かれており、それぞれ4章以外の項目で、1つづつのシーン項目を、
好印象度、悪印象度をパーセンテージで表記しており、両方のしゃべり方の印象がより伝わりやすいイメージになって、さらに印象が悪い方から説明を始めるためかイメージしやすく、
読み進めるたびに「自分がやってたことこんなに印象悪かったんだ」
「ここはこのしゃべり方あってたんだ」
「ここはもう1歩だったんだ」
それぞれのセクションで共感していく部分が多く納得が得られ、どのような対応が好印象なのか、より深く自分の中に落とし込むことのできる内容になってます。
例えば、損なしゃべり方が「相手の話をきっかけに自分の話を始める」得なしゃべり方が「相手が話し始めたら「聞き役」に徹する」という内容で、
最初に損な方の実例から入り、結果話し相手の話をさえぎるといった、非常に何が損なのかわかりやすい例になっており、そこから得の内容で損の部分を比較して話すので、どう話を進めていくと、得になれるのか非常にわかりやすい内容になってます。
ただし、作者は最後の締めくくりに、
「結局話の良し悪しとは、「相手がどう思うか」ですべて決まってしまうわけです」
といった少々厳しいこともおっしゃっており、あくまで道具であるしゃべり方だけでは100パーセント好印象は与えられず、なので作者も○○パーセントといった書き方をしており、
道具なので使ってみないと好印象にも悪印象にもならないので、まずは恐れず、いい印象を意識してみることが、この本を読んだ感想であり。
しゃべり方という道具を自分の中で深めれる1冊、
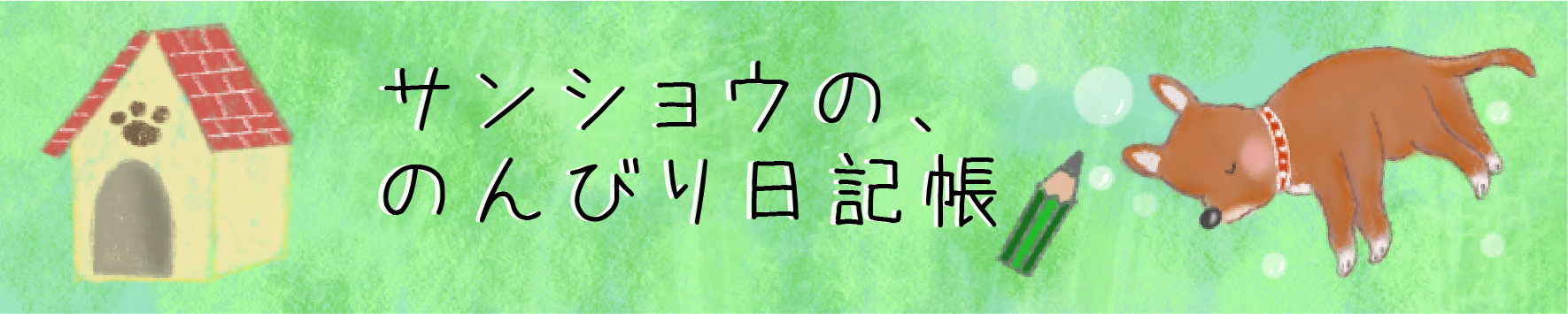






コメント